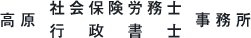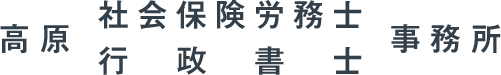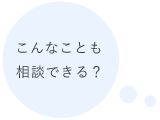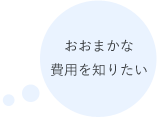障害年金
障害年金とは、病気や怪我により通常の日常生活や就労が制限されるようになってしまった場合に、一定の障害の状況の要件を満たす方が受給できる公的年金の一つです。
障害年金は理解しにくいうえ、多くの書類を準備したり、障害年金特有の細かなルールに基づき作成する必要があります。
実際に障害を抱えていらっしゃる方が、手続きのために年金事務所や医療機関に何度も足を運んだりするのは容易ではなく、書類の修正や訂正を指摘され本来の受給開始から遅れてしまったり、長い間かけて書類を整えた場合でも、認定してもらえないこともあります。
障害年金に関するご不明点や、申請手続きについてサポートさせていただきます。
申請の流れ
ヒアリング
- 障害の状態、初診日の確認、年金の加入歴等、受給要件の確認をします。
必要書類の作成
- 病歴の詳細や勤務状況等、詳細を伺い作成します。
診断書の依頼
- 医療機関に診断書の依頼をします。場合によっては受診状況等報告書も依頼します。
申請
- 必要書類を揃え、年金事務所へ提出します。
障害年金の種類
| 障害基礎年金 | 対象者:初診日に国民年金加入していた、20歳前の方 等級:1級または2級 生計を維持している子の加算あり |
|---|---|
| 障害厚生年金 | 対象者:初診日に厚生年金加入していた 等級:1級~3級 配偶者の加算あり |
| 障害共済年金 | 対象者:初診日に共済年金加入していた 等級:1級~3級 |
受給要件
1初診日
障害の原因となった傷病で初めて医療機関に行った日を証明できることが重要です。いくつかの医療機関を転院している場合は最初の医療機関の診察を受けた日が初診日となります。
・その障害について、医師の診察を受けている。
・年金加入期間に受診している。
・65歳未満である。
2保険料納付
初診日の前日における判断です。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
初診日を過ぎてから年金保険料を後納しても、保険料納付要件を満たすことはできません。
・初診日の前々月までに、納付済、免除を合わせた期間が全被保険者期間の2/3以上ある。
・初診日の前々月までの直近1年間に未納が無い。
3障害の状態
・障害認定日(初診日から1年6か月経過日)に、国が定める「障害認定基準」の1級~3級の状態である。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
初診日について
障害年金の請求において、初診日は非常に重要な要件になります。
初診日とは、障害の病名を判断された日ではなく、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転院があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
(例)体の不調が続き内科を受診し、改善せずメンタルクリニックへの受診を勧められ、その後うつ病と診断された →メンタルクリニックではなく、最初の内科受診が初診日となります。
医学的な初診日ではなく、障害年金独自の考え方もあります。
また、カルテの保存期間や廃院等により、初診日が特定ない場合もあります。
相当因果関係
障害の原因となった傷病がはっきりしない場合、「前の疾病や負傷が無かったら後の傷病は起こらなかったであろう」と判断される場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととし、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日となります。
社会的治癒
医学的には治癒していなくても、社会生活を問題なく一定の期間過ごせたことを客観的な判断で認められれば、一度治癒したとみなされ、同一の傷病で再度発症した場合は、初診日は再発した日になります。
(社会的治癒が判断されるケース)
・医療を行う必要がない状態であった
・症状が長期的に安定、消失していた
・ある程度の通常の社会生活を送っていた
※上記はあくまでも目安であり、明確な基準がないため個々の状況によって判断される旨ご了承ください。
初診日が特定できない場合でも、資料等を揃えることにより請求できる場合もありますので、先ずはご相談ください。
障害年金の請求時期
1障害認定日請求
・障害認定日から1年以内に請求を行います。
・障害認定日に受給権が発生し、その属する月の翌月分から支給されます。
・障害認定日以後3か月以内の診断書が必要です。
何らかの理由で障害認定日から1年以内に障害年金の請求をしなかった場合に、障害認定日から現在までを遡って請求します。(遡及請求)
その場合、障害認定日以後3か月以内の診断書及び請求日以前3か月以内の診断書、計2枚必要です。
※遡及して受けられる年金は、時効の関係で最大5年分が限度です。
2事後重症請求
・障害認定日に障害認定基準に該当しない場合でも、その後症状が悪化し、障害認定基準になったときに請求し
ます。
・請求日以前3か月以内の診断書が必要です。
・請求日に受給権が発生し、その翌月分から支給されます。